会報3号を発刊しました。寄稿者2名の方の寄稿文が素晴らしいです。
「アクネ、うまいネ、自然だネ」の阿久根その①

「アクネ、うまいネ、自然だネ」の阿久根その②

阿久根その② 寺島宗則(旧名松木公安)の旧家松木家を訪ねました。阿久根市脇本槝之浦、入り江の静かな浜辺すぐ目の前にぽっかりと見事な小島が浮かんでいました。これが変名の由来といわれる寺島です。松木家は医師の伯父の家で、かれは長野家から養子として入っています。実家も丘の斜面のすぐ上にありました。槝之浦での生活は短かったのですが、故郷の想いは強かったのでしょうね。幕末から明治黎明期の活躍はすでにご存じでしょうが、薩英戦争、それに続く薩摩藩英国留学生派遣に同行使節団、帰国後は外務卿など外交に力を発揮し、伯爵となっています。
松木家の家は当時のまま現存していますが、松木家の子孫の方がこの家で生活すべく、改装中でした。形をそのまま残して下さるようで嬉しいことです。
[原口泉教授の野外歴史教室] 西郷隆盛「チョッシモタッ!・・の謎を解く根占のバス旅」
![[原口泉教授の野外歴史教室] 西郷隆盛「チョッシモタッ!・・の謎を解く根占のバス旅」 [原口泉教授の野外歴史教室] 西郷隆盛「チョッシモタッ!・・の謎を解く根占のバス旅」](https://kagoshima-shinhakken.net/wp-content/uploads/2016/06/IMG_1541-750x350.jpg)
2017/01/09(月祭) 「明治維新150年かごしま文化向上提案事業」のツアー第1弾として、「原口泉教授の野外歴史教室」で根占を旅します。根占での西郷さんの謎に迫ります。原口先生の現地での特別講座もあります。原口ワールド炸裂です。根占は深いですよ。更に助成金のおかげでツアー料金も格安となりました。
(これは 2016/09/04 のツアーを台風のため延期したツアーです。)
おかげさまで満席になりました。ありがとうございました。
島津義弘の生涯を旅する3弾「島津は屈せず!駆けろ義弘!」帖佐・加治木編

2017/01/29(日)
2年後の2019年は義弘公没後400年を迎えます。九州制覇まであと一歩、朝鮮の役では獅子奮迅の働き、関ヶ原の戦いでは世にいう”島津の退き口”で多くの家臣を失いながらも生還。生涯に53度の戦を切り抜けて、島津を守った戦国武将でした。
おかげさまで満席になりました。ありがとうございました。
詳細は義弘を旅する第3弾
祝 「西郷どん」2018年大河ドラマに決定!
第34回街歩き 西郷隆盛 その3「国会の開設が急務でごわす」南洲顕彰館・南洲墓地を歩く
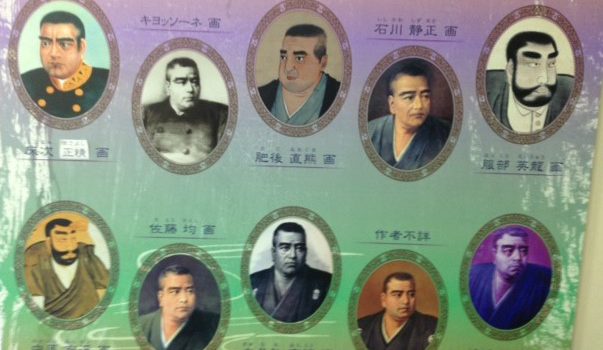
2016/11/24(木),11/27(日)
「この国の新しい形は国会を開設して、国民から選ばれた賢人達が万民の幸福の為に、私を捨てて働くことでごわす」と・・西郷さんは早くから唱えていました。西郷さんの人生に深く分け入ってみましょう。
千本いちょうと夕映えのデザートハウス

2016/12/04(日) 30年程前に都会から帰られたご夫妻が、荒れた山に手ずから植え続けられたいちょうが1200本になりました。全山がまっ黄色に染まる様は壮観です。鹿屋ばら園のすぐ近く、丘の上に南欧風の瀟洒な建物が・・・最近オープンしたお洒落なデザートハウス(南風農菓舎)です。これは行くしかないでしょう。
もっと知りたい!世界文化遺産へのとびら
2016/11/06(日) [明治維新150年かごしま文化向上提案事業]
日本近代化の魁となった、斉彬の集成館事業は我が国を列強国から守らねば、との強い決意からでした。在来技術を駆使して近代化に挑んだ先人たちの苦労が世界文化遺産の登録となったのです。この事業は表記の事業の助成金を頂いております。
詳細は・・世界文化遺産へのとびら
おかげさまで満席となりました。
出水の日本一厳し~い関所と甘~いみかん狩り
2016/11/26(土) 肥後との国境、野間之関は日本三大関所といわれ、中でも野間之関は龍馬や幾多の有名人が断念したという厳しい関所でした。そして甘いみかんの集積地出水、中でも立ち寄るところは特別です。ちぎったみかん一袋(約5K)はお持ち帰りです。晩秋の一日を愉しみましょう。
おかげさまで満席となりました。





