弥五郎どん祭りに行って来ました。まず人が多くてスゴイ!あの小さな町で(失礼)、あの沢山のプログラムをこなすのがスゴイ!午前1時、「弥五郎どんが起きっど!」と街じゅうをふれまわるのがスゴイ!岩川小学校の校標は「弥五郎どんのごっ」だそうです。スゴイ!1992年バルセロナ巨人博に参加した縁で爾来交流が続いているのだそうです。今回もバルセロナの若者が2人訪れてました。スゴイ!身の丈5mの巨人はやっぱり巨人伝説の体現者でした。スゴイ!巨人と言えば岩崎産業(株)の創業者岩崎與八郎翁の生誕地の顕彰碑をみてきました。生前もスゴかった!






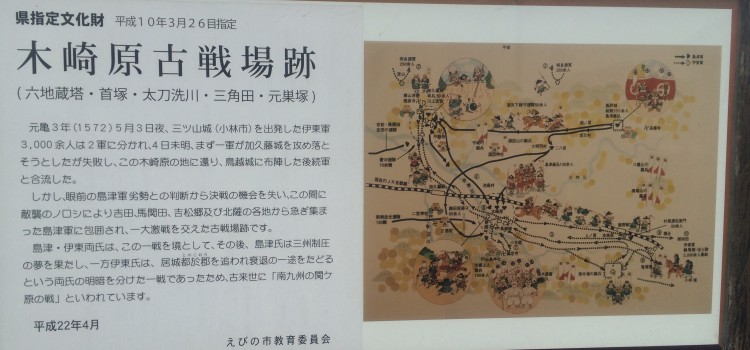
![IMG_1093[1]](https://kagoshima-shinhakken.net/wp-content/uploads/2014/04/IMG_10931-1024x768.jpg)


![IMG_1398[1]](https://kagoshima-shinhakken.net/wp-content/uploads/2014/09/IMG_13981-e1411695786514-768x1024.jpg)
![IMG_1399[2]](https://kagoshima-shinhakken.net/wp-content/uploads/2014/09/IMG_13992-e1411696727625-768x1024.jpg)



![IMG_0835[1]](https://kagoshima-shinhakken.net/wp-content/uploads/2014/08/IMG_08351-1024x768.jpg)

![IMG_1320[1]](https://kagoshima-shinhakken.net/wp-content/uploads/2014/07/IMG_13201-1024x768.jpg)
![IMG_1322[1]](https://kagoshima-shinhakken.net/wp-content/uploads/2014/07/IMG_13221-1024x768.jpg)